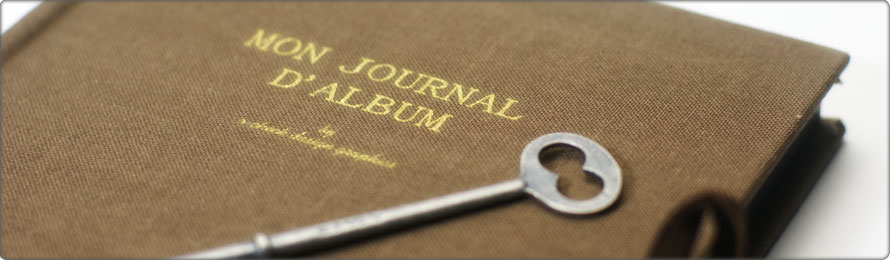
*経営事項審査とは、公共工事などを受注する場合に必要な入札参加資格を取得するために、審査機関の
データをもとに官公庁で経営の規模・総合評定値を決定する審査のことです。
*内容的には、建設業者の施行能力、財務の健全性、技術力等を判断する資料として、完成工事高、財務状況、
技術者数、社会貢献性を総合的に評価します。
*審査基準日は、申請する直前の営業年度の終了日(決算日)です。
*公共工事の請負契約締結可能な機関は、審査基準日より1年7ケ月に限られます。
従って、公共工事を請け負う場合、建設業者は決算確定後速やかに経営事項審査申請をする必要があり
ます。遅れた場合、審査結果通知書が届かず公共工事を契約できない場合がありますので注意が必要
です。
*総合点(P)は、経営状況(Y)と経営規模(X1・X2)、技術力(Z)、その他の審査 項目(W)の合計
となります。
P=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W で
最高点が 2,082点 最低点が 278点 です。
*売上志向より利益志向になりました。
特に、工事種類別完成工事高(X1)のウエイトが 35%から25% へ
自己資本額と利払前税引前償却前利益(X2)の絶対額を採用し 15%の評価
を与えています。
これは、利益のでない仕事(赤字受注)を否定した表示となっています。
大手や中堅企業に対して、利益額の差が大きな評点の格差をもたらします。
*第二に経営状況分析(Y)の大幅改正です。平成11年改正の体系では、不良債権処理問題の最中で
固定資産や有利子負債が財務内容のマイナス面の尺度とされていましたが、今回の改正で大幅に影響力
が低下しました。
しかし、純支払利息比率に最大のウエイトがあり、過大な負債が財務の健全さを圧迫することに変わり
ありません。
*Yの評価指数は、8指標となり、このうち「営業キャッシュフロー」「利益剰余金」の2指標の絶対額を採用し、
大手、中堅会社において大きな差をつけるものとなっています。
さらに、純支払利息比率、自己資本比率など評価点の上限、下限を厳しくして中小会社でもはっきりと
した格差がでます。
*第三に、社会性等(W)の評価指数を1.8倍に拡大し実質ウエイトも拡大しました。社会保険加入や
労働福祉の状況を評価する各項目、営業年度、防災協定の締結などの評価点を倍増しています。
この結果、Wの評価点は0〜1750点となり、とくに中小企業ではWの実質ウエイトは大幅に拡大
するとみられます。
☆技術者の常駐確認書類が変更となりました(決算期により2期分)
法人にあっては下記必数書類といずれか1つ(6ケ月1日分)
1.役員報酬手当等及び人件費の内訳
2.所得税源泉徴収簿
いずれか1つ
1.社会保険標準報酬額決定通知書
2.住民税特別徴収通知書(徴収義務者用+納税義務者用) が必要